episode16 アムネジア気取り

「何してるんだよ!!」
アーノルド!アーノルド!待って!
そう叫んだ時には井戸の底でバシャバジャと音を立てていたのが静かに止まる。
きっと視線をむけ睨んだ先には呆然と自身の手を見つめている彼が立っていた。
「どうして!!どうして彼を突き落としたんだよッッ!!」
彼の襟首を掴み詰め寄った。その視線がまじ合うことはなく彼はずっとその先を見つめていた。
「僕は違うんだ、君たちと違う。」

彼は狂ったように、噛み締めるようにその言葉を自分に言い聞かせている。
それがとても恐ろしくて思わず、足が怯んだ。
「ペル、セイ……?」
いつも見たいに笑う彼の顔が脳裏に浮かんで、その様子を信じられずに思わず彼の名前を確かめるように口に出した。
「…………」
「ペルセイ?」
「ハハ……」
「ペルセイじゃない!僕はペルセイじゃない!」
フロイドのその言葉を何度も何度も咀嚼して、しまいには君もそんなことを言うんだねとでも言いたげな目で彼がドッと笑いだした。
あまりに理解できないその言動に思わずヒッと声を出してしまう。
その瞬間に彼が力を込めて、フロイドの細く白い首に手を伸ばしギリギリと握った。
「僕は違う。君たちが罪人だとしても!僕は違うんだ!僕は帰るよ、ここが家だなんて僕は思ったことなんてない!ずっとずっと可笑しいと思っていたんだ……違う!なにもかも僕は……」
彼の目は首を絞めているフロイドのことなんて目に入っていない。ずっとその先の何かを見ているようでそれが酷く悲しくてフロイドは苦しみから目頭が熱くなっていくのを感じる。
「……う、そつ……き…!」
みんな嘘吐きだ。一緒にいるなんて簡単に口にして。結局は。
そう言ったフロイドの言葉に彼がハッと目を覚まして、その手を一瞬緩める。すぐにフロイドは身体をよじり彼から離れるようにして尻餅をついた。
倒れ込んだ先にあった小石が手に突き刺さり酷く痛かったけれど、そんなことさえどうでもいい。はやく逃げなくちゃいけないと彼の錯乱した表情をみて本能的に感じ取る。背中に冷や汗が流れるのを感じていた。
すぐさま、上体を起こしもつれる足を速く速くと彼を背にして走った。
「僕は、違うんだ。」
「みんなとはちがう。でも……」
僕を護ってください。
この身につけた名前を、英雄の名前を。
どうか。
____________
彼の足音と、違う違うと否定する声がした。
どうしても怖くて怖くて。
ただ、息を潜めて食堂に隠れ体を縮こませうずくまっていた。
いつだって、蹲ることしかできない自分が嫌だった。
「僕は違うんだ……。みんなを救わなきゃ、みんな……」
みんなを救わなきゃ。
「救う……だって?」
彼が、そういった言葉に思わず声が漏れた。
今ので彼に自分の居場所がバレたのも分かった、でもどうしてもその言葉が信じられなくて。何故、彼はそんな事を。理解出来ない。
「フロイド……?そこに居るの?」
その声はどうして逃げないのとでも言いたげで酷く悲しい声だった。
そんな風に言うなら、どうしてアーノルドをと疑問が募っていく。思えば、アイツもアイツだってみんな理解が出来なかった。
「死が救いだって……?巫山戯てる。俺は死にたくない。当たり前だろ、どうして死ななくちゃならないんだよ。可笑しいだろ、俺たちが何をしたっていうんだよ!何に怯えて死なないとならない?可笑しい。絶対に間違ってるだろ……!」
なのに、どうして皆は。
死を選べない自分が異端のようだった。そんなはずないだろ。死にたくないのが当たり前だろ。
フロイドはただ1人、訳が分からず生に執着しそれを否定出来ずにいた。
「君は分かっていないんだね、その先を。生きていたところで何があるの?もう君たちにはなにも成し遂げられない、なにも得られない、なにもないのに……」
「ひとりぼっちなんだよ……?」
可哀想だ。
そう彼が口にした途端に頭が沸騰しそうなほど感情が爆発しそうになった。
「可哀想だって!?誰がそんなことを言える!勝手に俺の人生を可哀想な事にするなよ!俺は俺は、ずっと……!俺は可哀想なんかじゃない!」
醜いなんて馬鹿にしないで。
シスターだけは……。
誰もそんなことを言って否定しないからここが……。
俺のやっとできた居場所だったのに。
「あぁ、可哀想に。きっと君は混乱しているだけだよ。」
そんな風に言う彼の目は、酷く辛そうで。
それなのにどうして。
「それなら、君はどうして」
「震えてるんだよ……」
ペルセイの手はふるふると震えて寒そうに凍えていて。
でも、誰もそれを握りしめることはもう出来なくて。
「……ッ‼︎僕は初めから違うんだ!ちがう!そんなふうに、そんな目で見ないでよ……」
「僕は……」
「ちがう……こんなの……こんなことは……」
ちがう。ちがうよ。ぜんぶちがう。
まちがってるんだ。
声にならないその感情は頬に伝う涙となって流れていく。でも、その哀しみだけは流れていくことはなく、心に振り積もっていくんだ。
それでも、彼の目はまるで大好きな彼女のように慈悲を帯びていて。その目で俺を殺そうとしていた。
それが俺たちに与える救いだと信じて疑わないようにして。ちがうよ。
って言った言葉が自分に言い聞かせているようだった。
違うと否定するその姿はもう、まるで。
「信じない、俺はだれも信じない。だから例え……」
「僕は違う、はやく家に帰らなきゃならないんだ……。でも、皆のことは救わわなきゃ。だって、皆は僕の……」


言葉にしようのない感情はどこに行くんだろう。
ふと、そんなくだらないことを考えていた。
気づけば目の前で倒れているのは彼だった。
英雄の名を被った彼だった。

俺は、立ち尽くす。
その場に広がる赤いドレスと。
おとこと。
俺が居る。
俺の手にはあの時のようなナイフが握られている。
死にたくにない。
そう呟いた。
______________
初めて、この教会を訪れた時に僕は思った。
何かが可笑しい。
家族との思い出に蓋をしたかのように今までの事を語らない子供たち、ずっと彼女に盲目的な信頼をよせていて何かが可笑しかった。
酷く不気味だったんだ。
僕は、僕だけは絶対に間違わない。
僕は彼らとは違う。
明日を願うことより、昨日を忘れないことを選んだ。
シスターやみんなのことは大好きだったけれど、絶対に心を預けることはしない。
本当を晒せば、もう二度と昨日に戻ることが出来ないような気がしたから。
僕に勇気をください。
そう言って僕は星に願った。あの星座を僕はきっと、外の世界でまた見ることになる。そう信じて疑うことは無かった。
本当に怖かったのは、僕が心を開けば開くほど大好きな人の存在が薄れていく気がしたこと。
みんなのことは確かに大好きだったよ。
嘘じゃない、これは嘘じゃなかった。
心からの言葉だったんだ。
真実を知った時に、僕は違うと思った。
皆がそう罪を犯した罪人だっていうなら、僕だけはきっと違うんだと思った。だって、僕は誰にも心を開かなかった。僕はきっと彼らとは違うんだ。
でも、大好きな彼らにしてあげることがあるなら僕は何だってしようと思った。
それなら、彼らを殺すことだって出来た。
それが救いなんだろう?
生きていたって、なにも救われないと彼らも分かっているんだろう?
だから、僕は。
信じられないとんでもない事をしていた。
ふと、自分の腹に刺さる包丁が見えた。
彼と攻防の末に結局、倒れていたのは僕だった。
ドロドロと流れていく血を見ていて僕はそこでやっと気づきました。
僕も皆と同じだったことに。
結局、死を恐れてそれでも心のどこかで死を望んでた。
アーノルドの背中を押した時に彼のことを見て、自分が本当に罪人でないなんて言えるのか怖くなった。
今更どうやって帰るのか、本当はその時から分からなかったのに。今更どうしたらいいのかも分からなくなっていたんだろう。
気分が優れない。
いや、いつも気分が悪いんだ。
ずっともやもやとした答えのない質問をされているみたい。
僕は、僕にもなりきれなければ。英雄にもなりきれない。どうも酷い病熱に侵されているように眠りにつくだけみたいだ。
目を瞑る。
暖かい思い出が瞼に焼き付いている。いつまでも、続けばいいと願ってしまっていた時点で僕はやっぱり罪人だったんだろうな。そう思って、目を瞑る。
もう少しここに居たら答えが出る気がしたけど、そんな時間すら神様はくれないみたい。
罪人の自分にお似合いの最後だった。
next……
彼は憂鬱
その鬱憤が誰かを傷つけることがないように

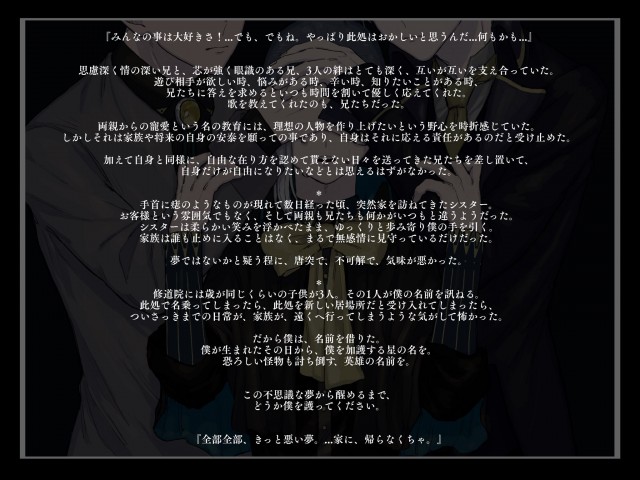


「何してるんだよ!!」
アーノルド!アーノルド!待って!
そう叫んだ時には井戸の底でバシャバジャと音を立てていたのが静かに止まる。
きっと視線をむけ睨んだ先には呆然と自身の手を見つめている彼が立っていた。
「どうして!!どうして彼を突き落としたんだよッッ!!」
彼の襟首を掴み詰め寄った。その視線がまじ合うことはなく彼はずっとその先を見つめていた。
「僕は違うんだ、君たちと違う。」

彼は狂ったように、噛み締めるようにその言葉を自分に言い聞かせている。
それがとても恐ろしくて思わず、足が怯んだ。
「ペル、セイ……?」
いつも見たいに笑う彼の顔が脳裏に浮かんで、その様子を信じられずに思わず彼の名前を確かめるように口に出した。
「…………」
「ペルセイ?」
「ハハ……」
「ペルセイじゃない!僕はペルセイじゃない!」
フロイドのその言葉を何度も何度も咀嚼して、しまいには君もそんなことを言うんだねとでも言いたげな目で彼がドッと笑いだした。
あまりに理解できないその言動に思わずヒッと声を出してしまう。
その瞬間に彼が力を込めて、フロイドの細く白い首に手を伸ばしギリギリと握った。
「僕は違う。君たちが罪人だとしても!僕は違うんだ!僕は帰るよ、ここが家だなんて僕は思ったことなんてない!ずっとずっと可笑しいと思っていたんだ……違う!なにもかも僕は……」
彼の目は首を絞めているフロイドのことなんて目に入っていない。ずっとその先の何かを見ているようでそれが酷く悲しくてフロイドは苦しみから目頭が熱くなっていくのを感じる。
「……う、そつ……き…!」
みんな嘘吐きだ。一緒にいるなんて簡単に口にして。結局は。
そう言ったフロイドの言葉に彼がハッと目を覚まして、その手を一瞬緩める。すぐにフロイドは身体をよじり彼から離れるようにして尻餅をついた。
倒れ込んだ先にあった小石が手に突き刺さり酷く痛かったけれど、そんなことさえどうでもいい。はやく逃げなくちゃいけないと彼の錯乱した表情をみて本能的に感じ取る。背中に冷や汗が流れるのを感じていた。
すぐさま、上体を起こしもつれる足を速く速くと彼を背にして走った。
「僕は、違うんだ。」
「みんなとはちがう。でも……」
僕を護ってください。
この身につけた名前を、英雄の名前を。
どうか。
____________
彼の足音と、違う違うと否定する声がした。
どうしても怖くて怖くて。
ただ、息を潜めて食堂に隠れ体を縮こませうずくまっていた。
いつだって、蹲ることしかできない自分が嫌だった。
「僕は違うんだ……。みんなを救わなきゃ、みんな……」
みんなを救わなきゃ。
「救う……だって?」
彼が、そういった言葉に思わず声が漏れた。
今ので彼に自分の居場所がバレたのも分かった、でもどうしてもその言葉が信じられなくて。何故、彼はそんな事を。理解出来ない。
「フロイド……?そこに居るの?」
その声はどうして逃げないのとでも言いたげで酷く悲しい声だった。
そんな風に言うなら、どうしてアーノルドをと疑問が募っていく。思えば、アイツもアイツだってみんな理解が出来なかった。
「死が救いだって……?巫山戯てる。俺は死にたくない。当たり前だろ、どうして死ななくちゃならないんだよ。可笑しいだろ、俺たちが何をしたっていうんだよ!何に怯えて死なないとならない?可笑しい。絶対に間違ってるだろ……!」
なのに、どうして皆は。
死を選べない自分が異端のようだった。そんなはずないだろ。死にたくないのが当たり前だろ。
フロイドはただ1人、訳が分からず生に執着しそれを否定出来ずにいた。
「君は分かっていないんだね、その先を。生きていたところで何があるの?もう君たちにはなにも成し遂げられない、なにも得られない、なにもないのに……」
「ひとりぼっちなんだよ……?」
可哀想だ。
そう彼が口にした途端に頭が沸騰しそうなほど感情が爆発しそうになった。
「可哀想だって!?誰がそんなことを言える!勝手に俺の人生を可哀想な事にするなよ!俺は俺は、ずっと……!俺は可哀想なんかじゃない!」
醜いなんて馬鹿にしないで。
シスターだけは……。
誰もそんなことを言って否定しないからここが……。
俺のやっとできた居場所だったのに。
「あぁ、可哀想に。きっと君は混乱しているだけだよ。」
そんな風に言う彼の目は、酷く辛そうで。
それなのにどうして。
「それなら、君はどうして」
「震えてるんだよ……」
ペルセイの手はふるふると震えて寒そうに凍えていて。
でも、誰もそれを握りしめることはもう出来なくて。
「……ッ‼︎僕は初めから違うんだ!ちがう!そんなふうに、そんな目で見ないでよ……」
「僕は……」
「ちがう……こんなの……こんなことは……」
ちがう。ちがうよ。ぜんぶちがう。
まちがってるんだ。
声にならないその感情は頬に伝う涙となって流れていく。でも、その哀しみだけは流れていくことはなく、心に振り積もっていくんだ。
それでも、彼の目はまるで大好きな彼女のように慈悲を帯びていて。その目で俺を殺そうとしていた。
それが俺たちに与える救いだと信じて疑わないようにして。ちがうよ。
って言った言葉が自分に言い聞かせているようだった。
違うと否定するその姿はもう、まるで。
「信じない、俺はだれも信じない。だから例え……」
「僕は違う、はやく家に帰らなきゃならないんだ……。でも、皆のことは救わわなきゃ。だって、皆は僕の……」


言葉にしようのない感情はどこに行くんだろう。
ふと、そんなくだらないことを考えていた。
気づけば目の前で倒れているのは彼だった。
英雄の名を被った彼だった。

俺は、立ち尽くす。
その場に広がる赤いドレスと。
おとこと。
俺が居る。
俺の手にはあの時のようなナイフが握られている。
死にたくにない。
そう呟いた。
______________
初めて、この教会を訪れた時に僕は思った。
何かが可笑しい。
家族との思い出に蓋をしたかのように今までの事を語らない子供たち、ずっと彼女に盲目的な信頼をよせていて何かが可笑しかった。
酷く不気味だったんだ。
僕は、僕だけは絶対に間違わない。
僕は彼らとは違う。
明日を願うことより、昨日を忘れないことを選んだ。
シスターやみんなのことは大好きだったけれど、絶対に心を預けることはしない。
本当を晒せば、もう二度と昨日に戻ることが出来ないような気がしたから。
僕に勇気をください。
そう言って僕は星に願った。あの星座を僕はきっと、外の世界でまた見ることになる。そう信じて疑うことは無かった。
本当に怖かったのは、僕が心を開けば開くほど大好きな人の存在が薄れていく気がしたこと。
みんなのことは確かに大好きだったよ。
嘘じゃない、これは嘘じゃなかった。
心からの言葉だったんだ。
真実を知った時に、僕は違うと思った。
皆がそう罪を犯した罪人だっていうなら、僕だけはきっと違うんだと思った。だって、僕は誰にも心を開かなかった。僕はきっと彼らとは違うんだ。
でも、大好きな彼らにしてあげることがあるなら僕は何だってしようと思った。
それなら、彼らを殺すことだって出来た。
それが救いなんだろう?
生きていたって、なにも救われないと彼らも分かっているんだろう?
だから、僕は。
信じられないとんでもない事をしていた。
ふと、自分の腹に刺さる包丁が見えた。
彼と攻防の末に結局、倒れていたのは僕だった。
ドロドロと流れていく血を見ていて僕はそこでやっと気づきました。
僕も皆と同じだったことに。
結局、死を恐れてそれでも心のどこかで死を望んでた。
アーノルドの背中を押した時に彼のことを見て、自分が本当に罪人でないなんて言えるのか怖くなった。
今更どうやって帰るのか、本当はその時から分からなかったのに。今更どうしたらいいのかも分からなくなっていたんだろう。
気分が優れない。
いや、いつも気分が悪いんだ。
ずっともやもやとした答えのない質問をされているみたい。
僕は、僕にもなりきれなければ。英雄にもなりきれない。どうも酷い病熱に侵されているように眠りにつくだけみたいだ。
目を瞑る。
暖かい思い出が瞼に焼き付いている。いつまでも、続けばいいと願ってしまっていた時点で僕はやっぱり罪人だったんだろうな。そう思って、目を瞑る。
もう少しここに居たら答えが出る気がしたけど、そんな時間すら神様はくれないみたい。
罪人の自分にお似合いの最後だった。
next……
彼は憂鬱
その鬱憤が誰かを傷つけることがないように

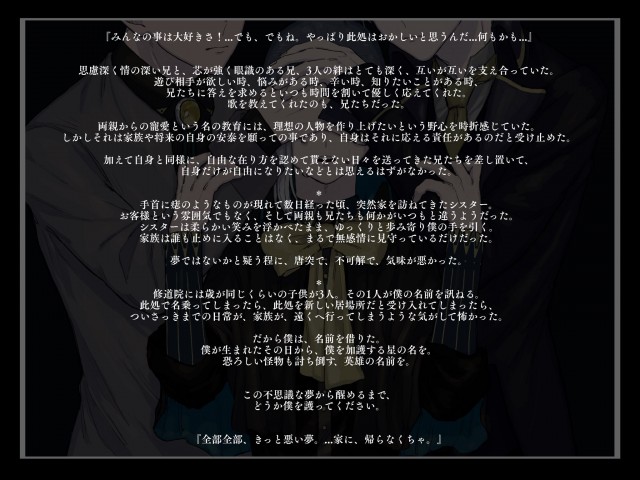

スポンサードリンク
COMMENT FORM