episode12 舌を抜く

「ガルシェ!!!」
呻き声を上げながら苦しみもがいて転がり込んだ彼の横には空になった小瓶がころころと音を立てている。
彼の状況は見るに堪えない姿になっていて、綺麗なままだった彼女とは正反対に酷く損傷が大きい。これが罪人に相応しい最後なのだと見せつけられた気がした。
フロイドがボロボロと涙を流して彼の血だらけになった体を揺さぶる。頭では分かっていた。彼女と彼が二度と目が覚めないことも。目の前にある死の恐怖から逃れようとしているのは誰なのか。
「そんな……どうして君まで」
分からない訳がなかった。
本当に分からない訳が無い。
だって俺達は同じだから。
同じ罪を抱えた罪人だ。
2人が死のうと思ったその気持ちが痛いほど分かる。
神に救いを求めたその行動が痛いほどわかる。
分かるのに、どうして自分たちが死なないとならないのか、未来を奪われる必要がどこにあったのか。
ただ生まれてきただけで罪があったのか。
そんな理不尽に嘆く自分がいた。
「……見ちゃだめだ」
ぐっと泣きたい気持ちを堪えた。
アーノルドだった。
誰よりも優しい彼ならきっとこの状況に今すぐ涙を流していたかもしれない。いや優しい彼だからこそ泣かずにいたのかもしれない。
その手で双子がそれから目を逸らすように誘導する。地下室の冷気に当てられたのか、2人の手は酷く冷たかった。
___________
崖崩れのように倒れていった2人の姿をみて、次は自分たちの番だと思った。
すみれ色の艶やかな髪が揺れる。
そっと自分たちの手を握ってくれていたアーノルドの手を離した。アーノルドが驚いた仕草を見せるが、彼の顔をみて微笑んでやれば彼はまた涙をこらえるようにぎゅっと目をつぶった。
止めるつもりはないようだ。
ここに来るまで恐怖で震えていた手が片割れに捕まれ、震えを止める。彼女の手は酷く生暖かくて生きていることを感じる。
「ねぇ、ミアおねぇちゃん」
「わかるよ、イザベラちゃん」
私たちはずっと一緒だよ、と目をみて笑い合えばほっとした。
「次にユーレイになるのは私だと思っていたの、本当はずっと分かってたのよ。」
イザベラは目を伏せて言った。
ミアの瞳に映る彼女にそっくりの自分を見るのが辛かった。
「私たちが罪人だなんて、本当にその通りで笑えないの」
罪を侵しました。
と断罪の時を逃れてきて、ようやく神様は私たちを懲らしめる気になったみたいね。
イザベラは自嘲めいた笑みを浮かべていた。
そんなイザベラをミアが心配そうに見つめ返して口を開く。
「そんな顔しないで、どうせミアお姉ちゃんと一緒なんだから怖いものなんてないの。」
だからずっと手を繋いでいて、いつまでも。
そんな言葉を口に出さなかった代わりにぎゅっとつないだ手に力を込めた。
視界の端に映る数々の拷問器具の1つに目を向ける。使い方なんて分からなかったけど、すっと手に取ればまるで何度も何度も繰り返したかのようにそれが手に馴染む。
「オモチャの銃とは違ってとっても重いみたい」
ぎこちない手つきで繋いだ手と反対の手でそれぞれが本物を手にした。
互いの額めがけ銃口を合わせる。試しにその引き金に手をあてるが思った以上に固いそれに驚く。細く小さく真っ白な手にはずいぶんと不釣り合いだった。
「またね」
1人が呟いて。
「ううん、違うよ。一緒に」
1人が話す。
怖い、怖い。怖いよ。
ユーレイになるのが怖い。
でも、それよりももう楽になりたかった。
2人の死をゆっくりと見届けていた。
止めるつもりがなかった。
何故か足が動かないなんて、言い訳してみたけれど本当は彼らの気持ちが分かるから止められなかったんだ。
だって、同じなんだもの。同じ苦しみなんだもの。
逃げ出したいと思って救いを求めるのが悪いことなんて私たちは思わない。
ただ、死でしか救われないなんて、死してなお救われるかなんて分からないなんて。
なんて。
なんて理不尽なんだろうと思った。
ゆっくりと時が進んで彼女の目に映る自分の瞳にも同じように彼女が写っている。
私たちが瓜二つでよかった。
目を閉じれば、この教会に来たことを次々と思い出いく。
楽しいだらけだった。
ここは暖かった。
ずっとここに居たいと思った。
みんなと……。
それはもう叶わない夢なのだと気づいてしまったの。
だから。
引き金は重い。
そっとその人差し指を……
ゆっくり、ゆっくりと…
「何してるの!やめて!2人とも!」

ばっと突然引かれた手に思わず狙っていたはずの銃口がズレる。
ズレた銃口の先にあったのは、その穢らわしくも美しい金の髪を振り乱して双子に手をのばすリンダ。
「り......んだおねぇ、ちゃ」
巻き込むつもりなんてなかったのに、どうして手を引いたりなんてしたの。どうして。彼女の顔に銃口が向いているのを目が捉えたが為す術もない。
次の瞬間、銃声が響いていた。
恐ろしくて思わず瞑ってしまった目を、涙で歪んだ視界を開く。
「お、……お」
「……お兄ちゃん……!?」

次の瞬間その場に倒れ込んだのは、リンダではなくローワンだった。

咄嗟に身体が動いたのか、彼がリンダの背中を押し自分が身代わりになったのだ。彼が肩を抑えて苦しんでいるのが恐ろしくて、先から煙が吹かせた銃を持つ手が震える。
なんてことをしてしまったの。そんな後悔より先にあったのは悲しみ。
それは言いしれない悲しみ。理解できなかった。リンダが自分たちを助けようとしたことも。それをローワンが助けたのも。
だって、私たちは罪人だ。
これ以上、生に執着したところでいずれは死ぬ人間だったんだ。これ以上、どうやって生きていけばいいの。その答えを誰も知らないのに、どうして私たちを助けたの。
それでも、肩を痛めたローワンを見てまだ自分たちの脈がある事にほっと息を撫でるような自分がいた。死にたいと思う心があるのに、死に脅えを抱く自分がいるのだ。
「貴方……!!なんで私を庇ったりして……」
どうして、どうしてみんな。涙が零れていく。
先を急ぐようにして死んでいくそんな皆の姿が恐ろしかった。なにより、自分が分からなかった。生きたいと思うの。
そう、思わなくちゃ……。
でも、だって。
答えがない。答えはない。誰も答えてくれない。
リンダの呼吸が荒れていき、肩で息をするように酷く混乱している様子だった。それを宥めるように肩を中心に全身へ走る痛みを抑えてローワンが彼女の背中をさすってやる。
脂汗が滲み、すぐにでも気を抜けば痛みに失神してしまいそうだった。自分がここで意識を失えば目が覚めた時には取り返しのつかない事になっている気がした。
いや、それより……。
「俺は大丈夫だよ、昔から丈夫なんだ……知ってんだろ?」
無理に笑って見せる彼の笑顔がひきつっていて、救いようのない後悔に襲われる。
「私が……ごめんなさい……」
ごめん。ごめん。謝る彼女からはいつものような気高さが感じられなかった。どんどんとその表情が曇っていくのを止められない。君にそんな顔して欲しかったわけじゃない。言おうとした言葉が形にならないのはきっと痛みのせいだ。
そんな彼女から視線を逸らし、こちらを黙ったまま見下ろす双子を見る。信じられないものをみたように2人がじっとこちらを見ていた。彼女達の銃を握る手はガタガタと震えているのだ。
「楽になりたいならその方法を手に取れよ。どのみちこの先に待ち受けてんのは地獄だけだぜ」
彼は優しい声音で彼女たちに言葉をかけた。それは止める言葉じゃなかった。
11歳の少女たちがこの先、なんの伝もなくなった世界で生きていく厳しさを彼は冷静に考えたんだろう。死が救いのように感じるなんて相当、思考が混乱しているんだろうか。
でも、残されたみちは僅かでそのどれもが茨の道なら誰もができるだけ短い道を選ぶような気がした。この選択が間違いかなんて、分かるはずがない。むしろ初めから間違っていたんだから。どのみちにすすんだって間違いだろ。
「……お姉ちゃん、お兄ちゃん。ごめんね」
「ごめんなさい。それでも、私たちは……」
その手を再度強く握りしめた。
「分かってる……」
誰も止めるものはいなかった。
分かってるんだ。
知ってるんだ。
本当に知らないのは、きっと……。
ペルセイが倒れ込んだローワンに肩を貸して彼を支える。体をふらつかせる妙に意気をなくしたリンダをアーノルドが起こしあげる。リンダが顔をあげれば彼の煌やかな金髪が目に入った。
5人は2人に背を向けた。それが最後のお別れだった。
4人は地下室で死ぬことを選んだんだ。また家族を亡くした。どうしたらいいかなんて誰も分からない。これが可笑しい事なんて今更誰かに言われた所で。初めから全ておかしかったんだからどうしようも無い。
やるせない感情を抱えたまま重い足取りで地下室を後にする。言葉を発した者は誰一人いなかった。カツカツと靴の音だけが響く。
ばいばい。
階段を登り終える頃、後ろから小さく銃声とさよならの声がした。
__________
「遠い東の国ではね、地獄にエンマサマがいるんだって」
「なぁにそれ」
イザベラがくすくす笑う声がする。彼女の笑い声はいつだって小鳥みたい。綺麗で小花がぽろぽろ飛んでいて、それが大好きだったの。
「怖い王様、とっても大きいんだから」
「大きい?どれくらいかしらおうちくらい?」
「ううん、もっとよ!お空くらい!」
空の大きさなんて分かるはずないわってまたイザベラがくすくすと笑っている。
ずっと聴いてたいな。
ずっと一緒にいたいな。
みんなともっと居たかったな。
「泣かないで、お姉ちゃん」
イザベラがそっとミアの頬を撫でる。気づけばその頬には涙が流れていた。
「私たちが悪い子じゃなかったら、シスターはずっと一緒にいてくれたのかな」
もう遅いのかな。もう手遅れなのかな。なにをどう謝ったって神様は許してくれないのかな。
「……ううん、ミアお姉ちゃん。あの子たちは……」
あの子たちはそんなこと教えてくれなかった。
いつかるはずのお別れをずっと待つのは辛いことだと私もお姉ちゃんも知っているの。
だから、私たちはこの銃を手に取ったのよ。
「そうよね、ごめんね。イザベラちゃん」
「ううん、何ともないわ」
今度こそ2人で。同じように互いに銃口を向けあった。
「エンマサマはね、嘘つきの舌を引っこ抜くんだって」
「……嘘つきの?」
「そうよ」
「もし引っこ抜かれたら私たち喋れなくなってしまうわ」
「そんなはずないよ、私たちに言葉なんていらないはすでしょう?」
「一緒にいればそれでいいの」
「ずっと一緒よ」
「離れ離れにならないようにずっと手を繋いでいようね」
「エンマサマがお空くらい大きいなら」
「地獄はもっと大きいわ」
「迷子にならないように」
「うん、手を繋ごう」
人差し指に力を込めた。

「怖くないよ」
嘘。
本当はすごく怖いけど、私たち嘘吐きだから。
「私も」
嘘。
でも、舌なんて無くなったっていい。
銃声が響く。
生まれた時も一緒だった。片割れが、いや自分が倒れていくのがゆっくりとみえた。
何時だって2人は一緒のまんまだ。
next……
彼女たちは虚飾
もうその口で誰かを惑わすような虚言を吐かないよう


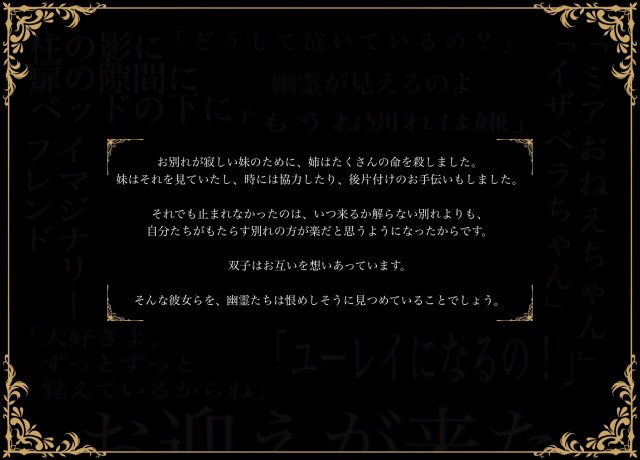

「ガルシェ!!!」
呻き声を上げながら苦しみもがいて転がり込んだ彼の横には空になった小瓶がころころと音を立てている。
彼の状況は見るに堪えない姿になっていて、綺麗なままだった彼女とは正反対に酷く損傷が大きい。これが罪人に相応しい最後なのだと見せつけられた気がした。
フロイドがボロボロと涙を流して彼の血だらけになった体を揺さぶる。頭では分かっていた。彼女と彼が二度と目が覚めないことも。目の前にある死の恐怖から逃れようとしているのは誰なのか。
「そんな……どうして君まで」
分からない訳がなかった。
本当に分からない訳が無い。
だって俺達は同じだから。
同じ罪を抱えた罪人だ。
2人が死のうと思ったその気持ちが痛いほど分かる。
神に救いを求めたその行動が痛いほどわかる。
分かるのに、どうして自分たちが死なないとならないのか、未来を奪われる必要がどこにあったのか。
ただ生まれてきただけで罪があったのか。
そんな理不尽に嘆く自分がいた。
「……見ちゃだめだ」
ぐっと泣きたい気持ちを堪えた。
アーノルドだった。
誰よりも優しい彼ならきっとこの状況に今すぐ涙を流していたかもしれない。いや優しい彼だからこそ泣かずにいたのかもしれない。
その手で双子がそれから目を逸らすように誘導する。地下室の冷気に当てられたのか、2人の手は酷く冷たかった。
___________
崖崩れのように倒れていった2人の姿をみて、次は自分たちの番だと思った。
すみれ色の艶やかな髪が揺れる。
そっと自分たちの手を握ってくれていたアーノルドの手を離した。アーノルドが驚いた仕草を見せるが、彼の顔をみて微笑んでやれば彼はまた涙をこらえるようにぎゅっと目をつぶった。
止めるつもりはないようだ。
ここに来るまで恐怖で震えていた手が片割れに捕まれ、震えを止める。彼女の手は酷く生暖かくて生きていることを感じる。
「ねぇ、ミアおねぇちゃん」
「わかるよ、イザベラちゃん」
私たちはずっと一緒だよ、と目をみて笑い合えばほっとした。
「次にユーレイになるのは私だと思っていたの、本当はずっと分かってたのよ。」
イザベラは目を伏せて言った。
ミアの瞳に映る彼女にそっくりの自分を見るのが辛かった。
「私たちが罪人だなんて、本当にその通りで笑えないの」
罪を侵しました。
と断罪の時を逃れてきて、ようやく神様は私たちを懲らしめる気になったみたいね。
イザベラは自嘲めいた笑みを浮かべていた。
そんなイザベラをミアが心配そうに見つめ返して口を開く。
「そんな顔しないで、どうせミアお姉ちゃんと一緒なんだから怖いものなんてないの。」
だからずっと手を繋いでいて、いつまでも。
そんな言葉を口に出さなかった代わりにぎゅっとつないだ手に力を込めた。
視界の端に映る数々の拷問器具の1つに目を向ける。使い方なんて分からなかったけど、すっと手に取ればまるで何度も何度も繰り返したかのようにそれが手に馴染む。
「オモチャの銃とは違ってとっても重いみたい」
ぎこちない手つきで繋いだ手と反対の手でそれぞれが本物を手にした。
互いの額めがけ銃口を合わせる。試しにその引き金に手をあてるが思った以上に固いそれに驚く。細く小さく真っ白な手にはずいぶんと不釣り合いだった。
「またね」
1人が呟いて。
「ううん、違うよ。一緒に」
1人が話す。
怖い、怖い。怖いよ。
ユーレイになるのが怖い。
でも、それよりももう楽になりたかった。
2人の死をゆっくりと見届けていた。
止めるつもりがなかった。
何故か足が動かないなんて、言い訳してみたけれど本当は彼らの気持ちが分かるから止められなかったんだ。
だって、同じなんだもの。同じ苦しみなんだもの。
逃げ出したいと思って救いを求めるのが悪いことなんて私たちは思わない。
ただ、死でしか救われないなんて、死してなお救われるかなんて分からないなんて。
なんて。
なんて理不尽なんだろうと思った。
ゆっくりと時が進んで彼女の目に映る自分の瞳にも同じように彼女が写っている。
私たちが瓜二つでよかった。
目を閉じれば、この教会に来たことを次々と思い出いく。
楽しいだらけだった。
ここは暖かった。
ずっとここに居たいと思った。
みんなと……。
それはもう叶わない夢なのだと気づいてしまったの。
だから。
引き金は重い。
そっとその人差し指を……
ゆっくり、ゆっくりと…
「何してるの!やめて!2人とも!」

ばっと突然引かれた手に思わず狙っていたはずの銃口がズレる。
ズレた銃口の先にあったのは、その穢らわしくも美しい金の髪を振り乱して双子に手をのばすリンダ。
「り......んだおねぇ、ちゃ」
巻き込むつもりなんてなかったのに、どうして手を引いたりなんてしたの。どうして。彼女の顔に銃口が向いているのを目が捉えたが為す術もない。
次の瞬間、銃声が響いていた。
恐ろしくて思わず瞑ってしまった目を、涙で歪んだ視界を開く。
「お、……お」
「……お兄ちゃん……!?」

次の瞬間その場に倒れ込んだのは、リンダではなくローワンだった。

咄嗟に身体が動いたのか、彼がリンダの背中を押し自分が身代わりになったのだ。彼が肩を抑えて苦しんでいるのが恐ろしくて、先から煙が吹かせた銃を持つ手が震える。
なんてことをしてしまったの。そんな後悔より先にあったのは悲しみ。
それは言いしれない悲しみ。理解できなかった。リンダが自分たちを助けようとしたことも。それをローワンが助けたのも。
だって、私たちは罪人だ。
これ以上、生に執着したところでいずれは死ぬ人間だったんだ。これ以上、どうやって生きていけばいいの。その答えを誰も知らないのに、どうして私たちを助けたの。
それでも、肩を痛めたローワンを見てまだ自分たちの脈がある事にほっと息を撫でるような自分がいた。死にたいと思う心があるのに、死に脅えを抱く自分がいるのだ。
「貴方……!!なんで私を庇ったりして……」
どうして、どうしてみんな。涙が零れていく。
先を急ぐようにして死んでいくそんな皆の姿が恐ろしかった。なにより、自分が分からなかった。生きたいと思うの。
そう、思わなくちゃ……。
でも、だって。
答えがない。答えはない。誰も答えてくれない。
リンダの呼吸が荒れていき、肩で息をするように酷く混乱している様子だった。それを宥めるように肩を中心に全身へ走る痛みを抑えてローワンが彼女の背中をさすってやる。
脂汗が滲み、すぐにでも気を抜けば痛みに失神してしまいそうだった。自分がここで意識を失えば目が覚めた時には取り返しのつかない事になっている気がした。
いや、それより……。
「俺は大丈夫だよ、昔から丈夫なんだ……知ってんだろ?」
無理に笑って見せる彼の笑顔がひきつっていて、救いようのない後悔に襲われる。
「私が……ごめんなさい……」
ごめん。ごめん。謝る彼女からはいつものような気高さが感じられなかった。どんどんとその表情が曇っていくのを止められない。君にそんな顔して欲しかったわけじゃない。言おうとした言葉が形にならないのはきっと痛みのせいだ。
そんな彼女から視線を逸らし、こちらを黙ったまま見下ろす双子を見る。信じられないものをみたように2人がじっとこちらを見ていた。彼女達の銃を握る手はガタガタと震えているのだ。
「楽になりたいならその方法を手に取れよ。どのみちこの先に待ち受けてんのは地獄だけだぜ」
彼は優しい声音で彼女たちに言葉をかけた。それは止める言葉じゃなかった。
11歳の少女たちがこの先、なんの伝もなくなった世界で生きていく厳しさを彼は冷静に考えたんだろう。死が救いのように感じるなんて相当、思考が混乱しているんだろうか。
でも、残されたみちは僅かでそのどれもが茨の道なら誰もができるだけ短い道を選ぶような気がした。この選択が間違いかなんて、分かるはずがない。むしろ初めから間違っていたんだから。どのみちにすすんだって間違いだろ。
「……お姉ちゃん、お兄ちゃん。ごめんね」
「ごめんなさい。それでも、私たちは……」
その手を再度強く握りしめた。
「分かってる……」
誰も止めるものはいなかった。
分かってるんだ。
知ってるんだ。
本当に知らないのは、きっと……。
ペルセイが倒れ込んだローワンに肩を貸して彼を支える。体をふらつかせる妙に意気をなくしたリンダをアーノルドが起こしあげる。リンダが顔をあげれば彼の煌やかな金髪が目に入った。
5人は2人に背を向けた。それが最後のお別れだった。
4人は地下室で死ぬことを選んだんだ。また家族を亡くした。どうしたらいいかなんて誰も分からない。これが可笑しい事なんて今更誰かに言われた所で。初めから全ておかしかったんだからどうしようも無い。
やるせない感情を抱えたまま重い足取りで地下室を後にする。言葉を発した者は誰一人いなかった。カツカツと靴の音だけが響く。
ばいばい。
階段を登り終える頃、後ろから小さく銃声とさよならの声がした。
__________
「遠い東の国ではね、地獄にエンマサマがいるんだって」
「なぁにそれ」
イザベラがくすくす笑う声がする。彼女の笑い声はいつだって小鳥みたい。綺麗で小花がぽろぽろ飛んでいて、それが大好きだったの。
「怖い王様、とっても大きいんだから」
「大きい?どれくらいかしらおうちくらい?」
「ううん、もっとよ!お空くらい!」
空の大きさなんて分かるはずないわってまたイザベラがくすくすと笑っている。
ずっと聴いてたいな。
ずっと一緒にいたいな。
みんなともっと居たかったな。
「泣かないで、お姉ちゃん」
イザベラがそっとミアの頬を撫でる。気づけばその頬には涙が流れていた。
「私たちが悪い子じゃなかったら、シスターはずっと一緒にいてくれたのかな」
もう遅いのかな。もう手遅れなのかな。なにをどう謝ったって神様は許してくれないのかな。
「……ううん、ミアお姉ちゃん。あの子たちは……」
あの子たちはそんなこと教えてくれなかった。
いつかるはずのお別れをずっと待つのは辛いことだと私もお姉ちゃんも知っているの。
だから、私たちはこの銃を手に取ったのよ。
「そうよね、ごめんね。イザベラちゃん」
「ううん、何ともないわ」
今度こそ2人で。同じように互いに銃口を向けあった。
「エンマサマはね、嘘つきの舌を引っこ抜くんだって」
「……嘘つきの?」
「そうよ」
「もし引っこ抜かれたら私たち喋れなくなってしまうわ」
「そんなはずないよ、私たちに言葉なんていらないはすでしょう?」
「一緒にいればそれでいいの」
「ずっと一緒よ」
「離れ離れにならないようにずっと手を繋いでいようね」
「エンマサマがお空くらい大きいなら」
「地獄はもっと大きいわ」
「迷子にならないように」
「うん、手を繋ごう」
人差し指に力を込めた。

「怖くないよ」
嘘。
本当はすごく怖いけど、私たち嘘吐きだから。
「私も」
嘘。
でも、舌なんて無くなったっていい。
銃声が響く。
生まれた時も一緒だった。片割れが、いや自分が倒れていくのがゆっくりとみえた。
何時だって2人は一緒のまんまだ。
next……
彼女たちは虚飾
もうその口で誰かを惑わすような虚言を吐かないよう


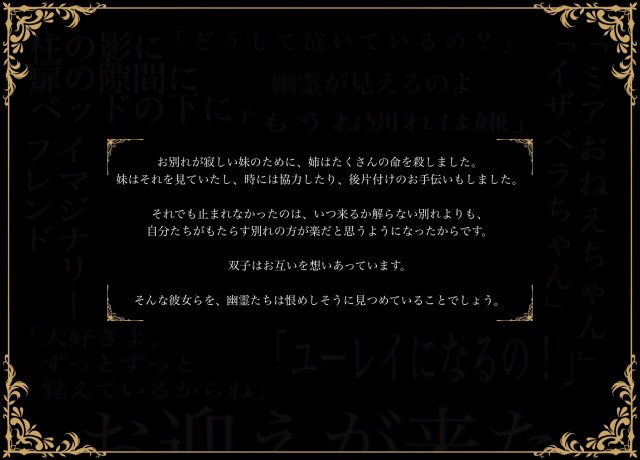
スポンサードリンク
COMMENT FORM