episode17 レムからサヨナラ

目の前に倒れる彼を見つめる自分がいる。
俺は何処から間違えていたんだろう。
手についたのは真っ赤な真っ赤なイチゴジャム?
違う。これは、血だった。
真っ赤な血だ。
覚束無い足取りであの場所へ向かう。
もしかしたら、もしかしたらいつもみたいに微笑んだ笑顔を浮かべるあの人がいるかもしれない。
そう思って進んだ。
後ろを振り返ることはしなかった。
彼の様子が可笑しいことはわかっていたし、あそこでそうしなければ俺は死んでいた。彼の目がそれを物語っていたんだ。だから俺は悪くない。
生きるためだ。何をしたっていい。
だから俺は悪くない。
俺は何も信じない。罪人だなんて聞いて呆れる。みんな頭が狂っているだけだろ、どうしてそんな御伽噺信じて死ななきゃならないんだ。
巫山戯てるだろう、はやく会いたい。
今すぐその暖かい手で包み込んで嫌なことなんて何も無いよって言って欲しかった。
ずっと彼女は俺を守ってくれたんだ。
嫌なことから目を逸らしたっていいって教えてくれた。眠れない夜には、手を握ってくれた。俺の髪を撫でてキスをしておやすみなさいって言って。
また、笑ってよ。シスター。
そっと血にまみれたベトベトの手で彼女の部屋の前、ドアノブを掴み立ち止まる。
後ろを振り返った。
気づけば変な匂いがする、油のような何か。気付かないふりをした。何も知らないフリをしてそっとそのドアを開けて中に入る
誰のものかもわからない血がぽたぽたと彼女の部屋のフローリングにシミを作り出していく。たしかに自分のものでないことだけは確かだったようだ。
やはり、誰もいないその部屋の様子に何処かほっとする自分がいた。本当に彼女がそこに居たらどんな風な表情を見せたんだろう。それを想像するのが怖かった。
いたむ心臓を抑えて、震える足を止めるように彼女の真っ白なシーツが貼られたベッドへと倒れ込んだ。
ぼふんっと心地いい音がする。
彼女の匂いと、暖かな日差しに照らされた布団の香り。このまま、二度と夜が来ないように眠ってしまいたい。
真っ白なシーツに滑稽なイチゴジャム。

目を瞑る。
思い浮かんだのは、みんなのこと。
馬鹿馬鹿しい。
罪人だなんて嘘に踊らされてあんなふうに最後を迎えるなんて。俺は絶対に信じない。俺は可哀想なんかじゃない。
俺は、幸せになるんだ。
此処で、教会で、シスターと、みんなと……。
「…………」
「……俺以外、誰もいないじゃないかッ‼︎‼︎」
枕に話しかける。返事はない。誰も返事をしてくれない。
それもそうだろう。誰もいないんだから。
静かな教会で轟轟と何かが燃えていくのだけが聞こえる。
気付かないふりをした。
アイツの仕業だと何となく察しが付いたけど、そう思いたくなかったんだ。どうして、諦めた。生きていくことを選ばなかった。
みんな俺を置いていく、死ぬのが怖い俺だけがずっとそこに取り残されて異端者のように扱われる。
そんなのおかしいだろう。
おかしいって何度も嘆いても誰も助けてくれやしなかった。
その答えは既に、明るみになっていて、後は信じて胸を預けて明日にさよならするだけ。
それを出来ないものだけが残されて、それを選べたものだけがまた明日を迎えられる。
目からこぼれ落ちたそれが哀しみからか、悔しさからか、やっと死を迎えられる喜びからか分からなかった。なにもかも分からないままだった。
ただ、死ぬのは怖い。
やっぱり、死にたくないんだ。
守ってよ、シスター。
そう思っても無駄なことを知っているのに願わずにはいられない自分が滑稽で嫌いだった。
いっそ嫌いになれたら良かった。
みんなのことも、シスターのことも。
でも、どうしたって俺たちは互いの傷を舐め合うだけの存在だったんだ。
心の拠り所をいつだって探して依存するようだった。
それでも、未来は輝いているものだと思っていたけど。
罪とは重いものでそれだけで自分たちに鎖をするようなものだった。
この先煙がこの部屋に充満して、眠ったままの俺は死んでいくだろう。
今、今ならまだ間に合うかもしれない。今から逃げれば助かるかもしれない。きっとまだ、火の手はそこまで上がっていない。命だけは助かるかもしれない。
逃げよう。
何処か遠くへ。
一人でも。
独りぼっちで何処へ?
そう思って、体を起こそうとした。
独りぼっち
誰も、手を差し伸べてくれることはない。
朝は一人で迎えて、朝食は一人で。
そんな朝を平気で過ごせる?
どうやったって、何もする気にはならなかった。
この先に待ち受ける未来にみんなが居ないから。ひとりぼっちだから。
寂しさを紛らわすように1人、自分を抱きしめるようにして固く目を閉じた。
「シスター……」
どこに行ってしまったんだろう。いつの日か居なくなっていた彼女のことを思い浮かべる。ずっと、ずっと居ない。彼女がいない。どこに行ったかは分かっていたけど、知らないふりをしてた。
サヨナラくらい、言わせてほしい。
挨拶は嫌いだったのに最後の最後でこんなことを思う事になるなんて想像もしなかった。
全て想像の仕様のない現実だった。でも、いつかくる未来だと過去から分かるそんな未来だった。
重たい足を引き摺って。重たい瞼を閉じて。
俺は今から眠るんだ。
明日が来ないってのは、暖かい陽射しの中で包まれているように安心できた。その反面、寝転ぶ背中だけは酷く冷えている。
もう明日に怯える必要がないとほくそ笑んだまま、疲れたからだを彼女のベッドに沈めていく。
羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹。
100匹を超えてもまだ寝れないなら、また1からやり直せばいい。
何度目かの99匹を超えた時、静かに眠りにつく。
怖いことは何も無いよ。
この先には何も無いよ。
熱さに身を焦がれた昨日を俺たちは忘れて眠る。
そしてもう何度目が覚めた時、決まって同じことを繰り返す
盲目だった。
最後まで気付かないふりばかり。
もう怖くないと思ったら、今日はよく眠れた。
おやすみ。

next……
彼は怠惰。
もう二度と寝過ごすような過ちを犯さないように
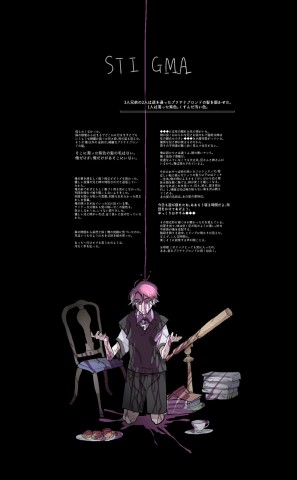



目の前に倒れる彼を見つめる自分がいる。
俺は何処から間違えていたんだろう。
手についたのは真っ赤な真っ赤なイチゴジャム?
違う。これは、血だった。
真っ赤な血だ。
覚束無い足取りであの場所へ向かう。
もしかしたら、もしかしたらいつもみたいに微笑んだ笑顔を浮かべるあの人がいるかもしれない。
そう思って進んだ。
後ろを振り返ることはしなかった。
彼の様子が可笑しいことはわかっていたし、あそこでそうしなければ俺は死んでいた。彼の目がそれを物語っていたんだ。だから俺は悪くない。
生きるためだ。何をしたっていい。
だから俺は悪くない。
俺は何も信じない。罪人だなんて聞いて呆れる。みんな頭が狂っているだけだろ、どうしてそんな御伽噺信じて死ななきゃならないんだ。
巫山戯てるだろう、はやく会いたい。
今すぐその暖かい手で包み込んで嫌なことなんて何も無いよって言って欲しかった。
ずっと彼女は俺を守ってくれたんだ。
嫌なことから目を逸らしたっていいって教えてくれた。眠れない夜には、手を握ってくれた。俺の髪を撫でてキスをしておやすみなさいって言って。
また、笑ってよ。シスター。
そっと血にまみれたベトベトの手で彼女の部屋の前、ドアノブを掴み立ち止まる。
後ろを振り返った。
気づけば変な匂いがする、油のような何か。気付かないふりをした。何も知らないフリをしてそっとそのドアを開けて中に入る
誰のものかもわからない血がぽたぽたと彼女の部屋のフローリングにシミを作り出していく。たしかに自分のものでないことだけは確かだったようだ。
やはり、誰もいないその部屋の様子に何処かほっとする自分がいた。本当に彼女がそこに居たらどんな風な表情を見せたんだろう。それを想像するのが怖かった。
いたむ心臓を抑えて、震える足を止めるように彼女の真っ白なシーツが貼られたベッドへと倒れ込んだ。
ぼふんっと心地いい音がする。
彼女の匂いと、暖かな日差しに照らされた布団の香り。このまま、二度と夜が来ないように眠ってしまいたい。
真っ白なシーツに滑稽なイチゴジャム。

目を瞑る。
思い浮かんだのは、みんなのこと。
馬鹿馬鹿しい。
罪人だなんて嘘に踊らされてあんなふうに最後を迎えるなんて。俺は絶対に信じない。俺は可哀想なんかじゃない。
俺は、幸せになるんだ。
此処で、教会で、シスターと、みんなと……。
「…………」
「……俺以外、誰もいないじゃないかッ‼︎‼︎」
枕に話しかける。返事はない。誰も返事をしてくれない。
それもそうだろう。誰もいないんだから。
静かな教会で轟轟と何かが燃えていくのだけが聞こえる。
気付かないふりをした。
アイツの仕業だと何となく察しが付いたけど、そう思いたくなかったんだ。どうして、諦めた。生きていくことを選ばなかった。
みんな俺を置いていく、死ぬのが怖い俺だけがずっとそこに取り残されて異端者のように扱われる。
そんなのおかしいだろう。
おかしいって何度も嘆いても誰も助けてくれやしなかった。
その答えは既に、明るみになっていて、後は信じて胸を預けて明日にさよならするだけ。
それを出来ないものだけが残されて、それを選べたものだけがまた明日を迎えられる。
目からこぼれ落ちたそれが哀しみからか、悔しさからか、やっと死を迎えられる喜びからか分からなかった。なにもかも分からないままだった。
ただ、死ぬのは怖い。
やっぱり、死にたくないんだ。
守ってよ、シスター。
そう思っても無駄なことを知っているのに願わずにはいられない自分が滑稽で嫌いだった。
いっそ嫌いになれたら良かった。
みんなのことも、シスターのことも。
でも、どうしたって俺たちは互いの傷を舐め合うだけの存在だったんだ。
心の拠り所をいつだって探して依存するようだった。
それでも、未来は輝いているものだと思っていたけど。
罪とは重いものでそれだけで自分たちに鎖をするようなものだった。
この先煙がこの部屋に充満して、眠ったままの俺は死んでいくだろう。
今、今ならまだ間に合うかもしれない。今から逃げれば助かるかもしれない。きっとまだ、火の手はそこまで上がっていない。命だけは助かるかもしれない。
逃げよう。
何処か遠くへ。
一人でも。
独りぼっちで何処へ?
そう思って、体を起こそうとした。
独りぼっち
誰も、手を差し伸べてくれることはない。
朝は一人で迎えて、朝食は一人で。
そんな朝を平気で過ごせる?
どうやったって、何もする気にはならなかった。
この先に待ち受ける未来にみんなが居ないから。ひとりぼっちだから。
寂しさを紛らわすように1人、自分を抱きしめるようにして固く目を閉じた。
「シスター……」
どこに行ってしまったんだろう。いつの日か居なくなっていた彼女のことを思い浮かべる。ずっと、ずっと居ない。彼女がいない。どこに行ったかは分かっていたけど、知らないふりをしてた。
サヨナラくらい、言わせてほしい。
挨拶は嫌いだったのに最後の最後でこんなことを思う事になるなんて想像もしなかった。
全て想像の仕様のない現実だった。でも、いつかくる未来だと過去から分かるそんな未来だった。
重たい足を引き摺って。重たい瞼を閉じて。
俺は今から眠るんだ。
明日が来ないってのは、暖かい陽射しの中で包まれているように安心できた。その反面、寝転ぶ背中だけは酷く冷えている。
もう明日に怯える必要がないとほくそ笑んだまま、疲れたからだを彼女のベッドに沈めていく。
羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹。
100匹を超えてもまだ寝れないなら、また1からやり直せばいい。
何度目かの99匹を超えた時、静かに眠りにつく。
怖いことは何も無いよ。
この先には何も無いよ。
熱さに身を焦がれた昨日を俺たちは忘れて眠る。
そしてもう何度目が覚めた時、決まって同じことを繰り返す
盲目だった。
最後まで気付かないふりばかり。
もう怖くないと思ったら、今日はよく眠れた。
おやすみ。

next……
彼は怠惰。
もう二度と寝過ごすような過ちを犯さないように
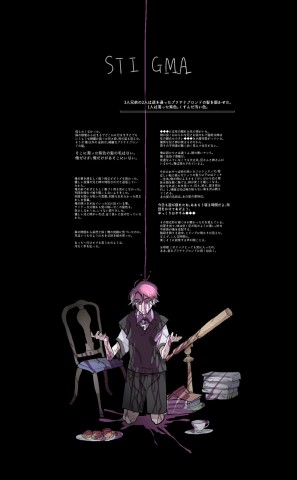


スポンサードリンク